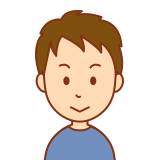
介護の現場で欠かせない存在となっている「福祉用具専門相談員」。利用者一人ひとりの生活を支えるため、最適な福祉用具を選定・提案する重要な仕事です。
本記事では、具体的な業務内容から資格取得の流れ、講習の内容、そして難易度までをわかりやすく解説します。介護業界でのスキルアップを目指す方や、新たなキャリアを検討している方におすすめの内容です。
福祉用具専門相談員の仕事内容とは?
福祉用具専門相談員の具体的な役割
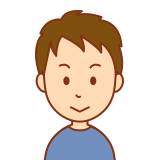
福祉用具専門相談員の仕事は、利用者一人ひとりの体の状態や生活環境に合わせて、最適な福祉用具を選び、安心して使えるようサポートすることです。
たとえば、どんな用具が生活に合うのかを一緒に考えたり、使用方法を丁寧に説明したりします。さらに、使い始めた後の点検や調整、利用状況の評価も大切な仕事の一部です。
こうしたサポートを通じて、利用者が自立した生活を取り戻したり、「これなら安心して暮らせる」と感じてもらえるよう手助けをしていきます。
どのような場で働く?活躍できる職場
福祉用具専門相談員の主な勤務先は、福祉用具の貸与・販売事業所です。
ほかにも、高齢者施設やリハビリテーション施設、訪問介護サービス事業所など、幅広い場所で活躍しています。また、福祉用具メーカーでセールスや商品管理などに携わる人もいます。
いずれの職場でも共通しているのは、利用者やその家族、介護職員としっかりコミュニケーションを取りながら、「この人にはどんな用具が合うのか」を考えていく点です。利用者に寄り添った提案ができるのは、この仕事ならではの魅力といえます。
利用者との関わりとやりがい
福祉用具専門相談員の仕事では、利用者やそのご家族との信頼関係がとても大切です。
福祉用具の選定や使用方法の説明を通して、「この相談員さんに頼んでよかった」と言ってもらえることも多く、感謝の言葉を直接いただけるのは大きな励みになります。
利用者が福祉用具を活用して「また自分で立てるようになった」「外に出かけられるようになった」といった変化を見せてくれる瞬間は、何よりもうれしく、やりがいを感じる場面です。
体力が必要?仕事の大変さと工夫
この仕事には、体力が必要な場面もあります。福祉用具の搬入や点検、調整など、意外と力仕事が多いんです。
また、利用者一人ひとりに合った用具を選ぶためには、慎重な確認や丁寧な説明も欠かせないので、精神的な集中力も求められます。
それでも、チームで協力して業務を分担したり、スケジュールを工夫して動くことで、負担を減らすことができます。
さらに、日々の業務を通して専門知識をアップデートしていくことで、自信を持って提案できるようになるのもこの仕事の魅力です。
福祉用具専門相談員になるには?資格取得の方法
資格取得に必要な条件とは?
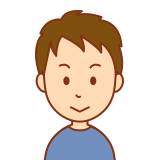
福祉用具専門相談員になるためには、「福祉用具専門相談員指定講習」を修了する必要があります。この講習は国(厚生労働省)が定める公的資格として認められており、特別な受講条件はありません。年齢・学歴・職歴を問わず、どなたでも受講できるのが特徴です。
講習を修了すると、正式に資格を取得したことになり、福祉用具の貸与・販売事業所などで働くための基準を満たすことができます。介護分野に初めて挑戦する方でも、基礎から学べる安心の資格です。
講習の内容とスケジュール
指定講習は、だいたい6日〜8日間ほどで、合計50時間以上のカリキュラムが組まれています。
学ぶ内容は多岐にわたり、「福祉用具の基本的な役割」「高齢者の日常生活の理解」などの基礎に加えて、「介護技術」「住環境と住宅改修」「福祉用具の特徴」など、実際の現場ですぐに役立つテーマが盛り込まれています。
最終日には修了試験が行われ、これに合格すると資格を取得できます。
スケジュールは講習を実施する機関によって多少異なりますが、短期間で集中して学ぶ形式が一般的です。仕事をしながらでも通える夜間講座や通信併用の講習を設けているところもあります。
受講対象者や講習会の選び方
この講習は、年齢や職歴を問わず誰でも受講できるため、高校卒業後に資格を取りたい方から、介護職や福祉業界へのキャリアチェンジを考えている社会人まで、幅広い層に人気があります。
講習会を選ぶ際は、まず「通いやすさ」を重視するのがおすすめです。自宅や職場からアクセスしやすい場所にあるスクールを選ぶと、無理なく通えます。
また、受講料やカリキュラムの内容は実施機関によって少しずつ異なるため、口コミや評判をチェックして、自分の目的に合った講習会を選ぶと良いでしょう。
資格の取得にかかる費用
福祉用具専門相談員指定講習の受講料は、全国平均で**約64,000円(税込70,400円)**ほどです。(この金額にはテキスト代や修了試験の費用も含まれています。)決して安いとはいえませんが、修了後は福祉用具貸与・販売事業所などで働くチャンスが広がり、キャリアアップにもつながります。
また、自治体によっては受講費用の一部を補助してくれる制度もあります。経済的な負担が気になる場合は、事前に自治体のホームページなどで確認しておくと安心です。
福祉用具専門相談員の資格の難易度と合格率
資格取得は簡単?それとも難しい?
福祉用具専門相談員の資格は国家資格ではなく、公的資格にあたります。取得するには「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、修了試験に合格する必要があります。
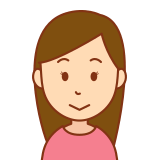
学歴や実務経験などの条件がないため、「比較的取りやすい資格」と言われることもありますが、実際には福祉用具や介護保険制度に関する専門知識を学ぶ内容が多く、初めて学ぶ方にとっては決して簡単とはいえません。
講習は50時間以上にわたり、6日〜8日間ほどの集中カリキュラムで行われるため、まとまった時間を確保する計画性も必要になります。
また、「福祉用具専門相談員の資格はきつい」と感じる人も少なくありません。その理由のひとつは、講習の中に実際の業務を想定した演習やシミュレーションが含まれているためです。
事前にテキストを読み込むなどの準備をしておかないと、修了試験に苦戦することもあります。つまり、やる気と事前準備が合格のカギと言えるでしょう。
合格率と失敗しないための対策
修了試験の合格率は比較的高く、しっかり講義を受けて内容を理解していれば、ほとんどの方が合格できるといわれています。とはいえ、「高い合格率だから大丈夫」と油断するのは禁物です。
試験では講義内容の理解度が問われるため、授業を聞き流すだけでは合格が難しくなる場合もあります。
対策としては、わからないことがあればその場で質問する姿勢を持つこと。そして、福祉用具の使用場面をイメージしながら学ぶと理解が深まりやすいです。
また、配布されたテキストや資料は繰り返し読み返し、特に福祉用具の特徴や利用計画作成のポイントなど、実務に直結する部分を重点的に押さえるのがおすすめです。
このように計画的に学べば、無理なく資格取得を目指すことができます。
介護職から福祉用具専門相談員に転職するケースも増加中
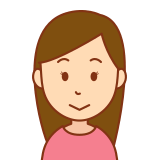
最近では、介護職から福祉用具専門相談員へ転職する方が年々増えています。
介護現場で培った知識や経験は、福祉用具専門相談員として働く際に大いに役立つため、比較的スムーズにキャリアチェンジできるのが特徴です。
介護職では直接利用者のケアにあたることが多いのに対し、福祉用具専門相談員はその支援をサポートする重要な役割を担います。そのため、違った形で利用者やご家族を支えるやりがいを感じられる仕事でもあります。
特に、介護現場で培った「利用者の体調や生活動線の把握」や「ご家族とのコミュニケーション力」といったスキルは、福祉用具専門相談員の仕事でも大きな強みになります。
たとえば、利用者それぞれの身体状況や生活環境に合った福祉用具を選定・調整し、適切なアドバイスを行う際に、介護現場での経験が土台となって、より具体的で現実的な提案ができるのです。
一方で、福祉用具専門相談員の業務には、事務作業や計画書の作成など、介護職とは少し異なる仕事も含まれます。そのため、キャリアチェンジの際にはこれらに慣れる努力も必要です。
また、資格取得のための指定講習の受講も必須ですが、講習自体は難易度が高くないため、多くの方が比較的スムーズに資格を取得しています。
介護職からの転職を考える理由としては、「体力的な負担を少し抑えたい」「より専門性を高めたい」といった声が多く聞かれます。
ただし、福祉用具専門相談員の現場でも、利用者への福祉用具の搬入や調整など、体力を必要とする場面はあります。そのため、工夫しながら業務に取り組むことが大切です。
それでも、利用者やご家族から直接「ありがとう」と感謝の言葉をもらえる機会が多いのは、この仕事ならではの魅力と言えるでしょう。


